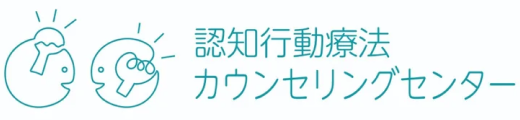2025年07月06日
- メンタルヘルス
【大阪でストレスチェックの導入を検討されている企業様へ】

~50人未満の事業所でも、実施する価値がある理由とは~
「うちのような少人数の職場にまでストレスチェックが必要なんでしょうか?」
「法律で義務化されると聞いたけど、具体的にどう動けばいいか分からない」
「やっても形だけになるのでは?意味があるのか不安です」
大阪エリアの経営者・人事担当者の皆さまから、こうしたご相談をいただくことが増えてきました。
実際、ストレスチェック制度を取り巻く状況は、大きな変化を迎えています。
2025年5月、労働安全衛生法が改正され、従業員が50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務付けられることが正式に決まりました。
これからは、事業所の規模にかかわらず、働く人のメンタルヘルスに配慮する取り組みが求められていきます。
この記事では、
- 法改正による変更点とスケジュール
- なぜストレスチェックが今、重要視されているのか
- 小規模な事業所でも“実施する意味”とは何か
について、大阪の地域特性を踏まえながら、わかりやすく解説していきます。
執筆は、天王寺・上本町エリアにある「認知行動療法カウンセリングセンター大阪店」。
当センター代表の岡村優希(臨床心理士・公認心理師)は、厚労省が定めるストレスチェック実施者の資格を持ち、職場のメンタルヘルス支援にも取り組んでいます。
1|法改正の要点:ストレスチェック義務化が全事業所対象に
2025年5月に成立した改正労働安全衛生法では、これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業所でも、ストレスチェックが法的義務として実施対象となることが決定しました。
| 対象 | 変更前 | 変更後(2025年改正) |
| 対象事業所 | 従業員50人以上のみ | すべての事業所が義務化対象 |
| 対象者 | 常時雇用されている労働者 | 全労働者が対象に |
| 目的 | 精神的な負担の把握 | 予防と早期発見に重点 |
| 実施時期 | – | 2028年頃から段階的施行予定 |
義務化の背景には、全国的な課題があります:
- 精神障害による労災認定件数が過去最多(2023年度:883件)
- メンタル不調による休職・離職が中小企業に大きなダメージを与えている
- 小規模事業所では“見えないストレス”が蓄積しやすい
こうした社会情勢を受け、すべての職場において、働く人の心の健康を守る視点が求められるようになったのです。
2|ストレスチェックの“本当の価値”とは?
ストレスチェックと聞くと、「スコアを出して終わり」「面談を希望するかどうかを聞いて終わる」といったイメージを持たれるかもしれません。
しかし、本質はそこではありません。
ストレスチェックは、“気づき”と“対話”の入口になるツールです。
◉ 個人にとっての役割
- 「自分は今、疲れている」と気づく機会になる
- 不調のサインに早めに対処できるようになる
- 抱えていた不安や負担を、言語化するきっかけになる
◉ 組織にとっての意味
- 職場のストレス要因(例:人間関係、業務量)を可視化できる
- 離職やパフォーマンス低下の“前兆”を捉えることができる
- 「声なき声」を拾い、改善に繋げる糸口になる
3|大阪の中小企業だからこそ“意味のある導入”になる
「少人数だし、みんなの状態は分かっているつもり」
「距離が近いから、わざわざアンケートを取らなくても…」
こうしたお声もよく伺いますが、実際には**“分かっているつもり”がリスクになりやすい**のが小規模職場の特徴です。
✅ 気づきにくい無理・我慢
少人数でまわしている現場では、「代わりがいない」という思いから、
不調を隠して無理を続けてしまうケースが多くあります。
✅ 突然の離職や休職のダメージが大きい
1人が抜けると業務が回らない職場では、予防的な取り組みの効果が大きいのです。
✅ チェックをきっかけに、対話の場ができる
「今までは何となく言いづらかったことも、話せるようになった」という感想も少なくありません。
4|制度対応だけで終わらせないために大切なこと
法的な義務として導入したとしても、
「やっただけ」「集計結果を見て終わり」では意味がありません。
ストレスチェックを**“現場を良くするための仕組み”として活用するには、次のような視点が大切です。**
● 実施の目的を整理する
「うちの職場では、何のためにストレスチェックを行うのか?」
目的が明確になれば、結果の捉え方や改善策も見えてきます。
● 結果を“対話の材料”として扱う
数値そのものではなく、
「なぜこのストレス要因が高いのか?」という視点で対話を行うことで、改善に向けた一歩になります。
● 小さな変化でOK
制度の導入=大がかりな改革ではありません。
「休憩の取り方を見直した」「上司との雑談時間を作った」など、小さな変化が安心感につながります。
5|よくあるご質問(Q&A)
Q. 義務化されたとはいえ、今すぐ準備しないといけませんか?
A. 施行は2028年頃とされていますが、準備は早めに始めておくのがおすすめです。
突然の制度対応で現場が混乱しないよう、今のうちから流れを整えておくことで余裕を持った運用が可能です。
Q. 人数が少ないと、匿名性が心配です…
A. 少人数の職場ほど、ストレスチェックの“対話的な活用”が有効です。
形式にとらわれず、外部支援やカスタマイズの方法を検討することも可能です。
Q. 受けても意味がないと思ってしまう社員がいそうで不安です
A. 実施の目的や結果の活かし方を共有することが、信頼につながります。
「形だけではない」と感じてもらえるよう、導入時の説明がとても重要です。
6|まとめ:制度の先にある“安心できる職場”づくりへ
ストレスチェックの義務化は、ただの制度対応ではなく、
「人が安心して働ける場所をつくる」ための土台作りです。
大阪の中小企業やサービス業、教育・医療・介護などの現場では、
“たまたま”の不調や“声にできなかった悩み”が、
突然の離職・休職につながることも珍しくありません。
その前に、「気づく」仕組みをつくっておくこと。
それこそが、ストレスチェックの本当の意味だと私たちは考えています。
📍認知行動療法カウンセリングセンター 大阪店
- 住所:〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-21 早川ビル303号室
- アクセス:近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩2分/谷町九丁目駅 徒歩5分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- Webサイト:https://osaka.cbt-mental.co.jp/
- ご相談フォーム:こちらからどうぞ