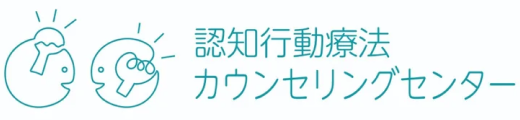2025年07月30日
- 認知行動療法
大阪の養護教諭に役立つ認知行動療法

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター大阪店です。
日々、保健室で生徒や保護者と向き合っておられる養護教諭の先生方。そんな皆さまの中には、以下のような思いを抱いたことはありませんか?
- 同じような相談が繰り返されて、どう対応すべきか悩む
- 保護者との面談が緊張する
- 生徒の不調の背景がうまくつかめない
こうしたお悩みに対して、**認知行動療法(CBT)**の視点を取り入れることで、対応の幅が広がることがあります。
“話を聴く”だけではない支援を目指して
保健室は、身体のケアにとどまらず、生徒のこころと向き合う大切な場所でもあります。
しかし、「どう声をかければいいのか」「何を意識して関わればよいのか」に迷う場面も多いはずです。
そこで今回は、学校現場でも取り入れやすいCBTのエッセンスを、現場の先生方向けにご紹介いたします。
養護教諭の先生が使いやすいCBTのステップ
認知行動療法は専門家だけのものではありません。日常の会話に取り入れやすい要素が多く、特に以下の3つは現場で実践しやすいとされています。
1.気持ち・体の反応・考え方の整理を促す
まず大切なのは、相手が「今どんな状態にあるのか」に気づけるような問いかけです。
- 「どんな気持ちやったん?」
- 「体のどこに力が入ってた?」
- 「そのとき、どんなふうに考えてたんやろ?」
こうしたやりとりを通じて、生徒自身が自分の状態を俯瞰する機会を持てるようになります。
2.繰り返される行動の“理由”を一緒に見つめる
たとえば、「しんどい時に保健室に来る」「同じことを何度も話す」といった行動には、短期的に不安を和らげる役割があることがよくあります。
その行動を責めるのではなく、「どんな気持ちが隠れてるのかな?」という姿勢で関わると、相手との信頼関係がより深まります。
3.“別のやり方”を一緒に考える提案
認知行動療法では、「こうしなさい」と変化を押し付けるのではなく、「こんなやり方もあるよね」と選択肢を広げることを重視します。
- 「もし次も似たようなことがあったら、どうしてみたい?」
- 「他にできそうなやり方ってあるかな?」
こうした問いかけが、生徒や保護者の“試してみよう”という気持ちを育てます。
保護者との関係にも活かせる視点
保護者からの相談では、時に強い口調や感情的な訴えに戸惑うこともあるかもしれません。
その際、表面的なやりとりにとどまらず:
- 何を一番不安に感じているのか
- どんな状況でその不安が大きくなるのか
- 対話の主導権を持ちすぎず、冷静に聞く姿勢を保つ
といった**“心の背景を読み解く視点”**が、関係を和らげる鍵になります。
よくある相談へのCBT的アプローチ
| 状況 | CBT的な対応 | 意図 |
| 保健室に繰り返し来る | 「その時、何を感じてたんかな?」 | 行動と感情の関係に気づく |
| 面談で保護者が感情的 | 「一番気になってることはどんなことでしょう?」 | 不安の本質に近づく |
| 生徒が話を繰り返す | 「今度はどうしてみる?」 | 新たな行動の提案 |
よくあるご質問(Q&A)
Q1:心理の専門知識がない私でもCBTを使ってよいのでしょうか?
A1:もちろん大丈夫です。CBTは、特別なスキルよりも、「どう関わるか」「どんな問いかけをするか」が大切です。先生方が普段されている関わりに少し視点を加えるだけで、効果的な支援になります。
Q2:保護者との面談で緊張してしまいます…
A2:「反応」ではなく「背景の理解」に焦点を当てることで、感情的なやりとりに巻き込まれにくくなります。相手の言葉に振り回されず、共感的に対応できる土台を整えましょう。
Q3:もっと学んでみたい場合はどうすれば?
A3:当センターでは、教職員向けの研修・勉強会のご依頼も受け付けています。校内での勉強会から外部研修まで、ニーズに応じた対応が可能です。
認知行動療法カウンセリングセンター大阪店のご案内
- 店舗名:認知行動療法カウンセリングセンター大阪店
- 住所:〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-21 早川ビル303号室
- アクセス:近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩2分、谷町九丁目駅 徒歩5分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://osaka.cbt-mental.co.jp/
認知行動療法の考え方は、「心の見方を変える」だけでなく、支援者自身の安心にもつながる実践知です。
保健室のやりとりに、ほんの少しだけ新しい視点を加えてみませんか?
一覧に戻る