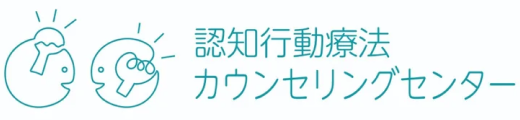2025年10月21日
- 認知行動療法
「めまい」にカウンセリングが有効!?/認知行動療法カウンセリングセンター大阪店

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター大阪店です。
本日のテーマは、めまい・耳鳴り・倦怠感・痛みなど、
“慢性的に続く身体症状へのカウンセリング”です。
身体症状には「急性期」と「慢性期」があります。
急性期では医学的な評価と治療が優先されますが、
重大な疾患の可能性は低いと判断されたあとにも、
症状だけが生活に居座り続ける場合があります。
症状が残ることで「以前は普通にできていたこと」が難しくなることがあります。
例えば、
・めまいで本や画面を読む時間が極端に限られる
・耳鳴りで静かな場所ほど落ち着けない
・予定を入れても体調で直前に諦めざるを得ない
こうした“生活上の制限”が積み重なると、
「この先どう暮らしていけばいいのか」という悩みに直面します。
この記事では、
「症状と付き合いながら、どう暮らしを取り戻していくか」
医療の次の段階にあたる支援としての認知行動療法(CBT)を紹介していきます。
身体症状への認知行動療法(CBT)とは
CBTは“症状を消すこと”を唯一の目的とせず、
症状と共に“暮らしを取り戻す” ことを支援の中心に据えます。
扱う中心は「症状」ではなく「生活」です。
- 何を取り戻したいのか
- どんな日常なら自分らしく過ごせるか
- 症状が強い日も最低限の暮らしを守れるか
- 悪い日にも“参加し続ける設計”を整えられるか
これは「感情コントロール」ではなく
“生活設計のリハビリ” に近い支援です。
苦しみの本質は「症状」ではなく「生活の縮小」
身体疾患CBTにおける回復指標は、
治療の成功=症状ゼロ
ではなく
QOLの回復=日常生活が戻ること
です。
- 仕事を続けられる
- 行きたい場所に行ける
- 役割・つながりを維持できる
- 症状に“人生を奪われない”
ここに支援のゴールがあります。
CBTが寄り添うのは「からだ」ではなく
“暮らしを取り戻したいという願い”
症状がゼロになる未来を待つのではなく、
症状がある現在でも暮らしを成立させる力 を育てていきます。
- 「耐える」ではなく「共に生きる」
- あきらめではなく「形を変えて続ける」
- 回避ではなく「生活の再設計」
CBTは、身体に起きていることと“生活を営む力”を再び結びつけます。
2025年10月19日開催:身体疾患CBTの第一線から学ぶ
この日の研修では、長年身体症状の臨床に携わってこられた
認知行動療法カウンセリングルーム Fig lab 代表
姜 静愛(かん ちょんえ)先生 をお招きしました。
姜先生の臨床は、
「症状と闘う」のではなく
「症状と共に生きる暮らしを再設計する」
という哲学に基づいています。
これは“症状を無くす治療”とは別の意味での「回復」であり、
身体疾患CBTの核心にある考え方です。
学びの中で強く残ったもの(主催者の感想)
特に心に残ったのは、技法以上に臨床家としての姿勢でした。
“症状のない未来”を約束することは誰にもできません。
しかし、“症状があっても生きられる現在”を支えることは今この瞬間からできる。
もし自分が当事者なら、
「症状を消してくれる人」ではなく、
「生活を共に取り戻す人」を選びたい。
姜先生はまさにその在り方を体現する臨床家だと感じました。
参加者の声(一部)
- 「『できそう』をともに支えることがCBTの核だと実感しました」
- 「症状ゼロ=成功という枠から解放され、支援の指標が見えました」
- 「慢性疼痛の支援中で迷いがあったが、生活回復モデルで整理できました」
よくある質問
Q1.症状が強い日は?
→ “できない日”ではなく“回復日”と位置づけます
Q2.医療で異常なしでも相談できる?
→ はい。そこから先の“生活”は心理支援の領域です。
Q3.回復の基準は?
→ 症状ゼロではなく「生活参加」が守れているかです。
ご予約・アクセス(大阪店)
認知行動療法カウンセリングセンター大阪店
https://osaka.cbt-mental.co.jp/
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-21 早川ビル303号室
(近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩2分/谷町九丁目駅 徒歩5分)
登壇講師
姜 静愛(かん ちょんえ)先生
公認心理師・臨床心理士/Fig lab代表
新潟大学大学院 現代社会文化研究科 博士後期課程
専門:身体疾患と心理支援(CBT)