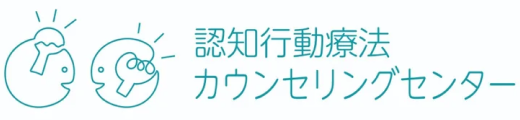2025年10月17日
- 認知行動療法
大阪でできる「心の整え方」― ストレス社会で“動じない自分”を取り戻す方法

最近、「整える」という言葉を耳にする機会が増えました。
身体を整える、生活を整える、空間を整える──。
けれども「心を整える」とは、いったいどういうことでしょうか。
身体であれば「風邪をひきにくくなる」「体力がつく」といった明確な効果がわかりやすいですが、
心の場合は目に見えず、「整える」と言われても実感しにくいものです。
大阪のような活気ある街では、日々の仕事や人付き合い、情報の多さの中で、
無意識のうちに心が疲れてしまう人も少なくありません。
そんな時に大切なのが、「心を整える」という考え方です。
本記事では、認知行動療法(CBT)の視点から、
「心を整える」とは何を意味し、どんな具体的な利点があるのかをわかりやすく解説します。
1. 「心を整える」とはどういう状態か
「整える」とは、乱れているものを整序し、自然なバランスを取り戻すこと。
つまり、「心を整える」とは──
感情や思考に飲み込まれず、現実をありのままに見て、冷静に選択できる状態
のことを指します。
認知行動療法では、この状態を「認知的柔軟性(Cognitive Flexibility)」と呼びます。
たとえば、仕事でミスをしたときに「もう終わりだ」と決めつけず、
「誰にでもあること」「次にできる対策を考えよう」と捉えられる状態です。
この柔軟さがあると、感情や行動を自分でコントロールできるようになります。
逆に、心が乱れている時は、思考が狭くなり、極端な判断をしがちです。
2. 心を整えることで得られる5つの利点
では、心を整えることでどんな変化が起こるのでしょうか。
認知行動療法の理論や臨床データを踏まえ、5つの具体的な利点をご紹介します。
① 認知・判断の精度が上がる
心が整っていると、出来事を“そのまま”受け止められます。
感情に引きずられず、「事実」と「解釈」を分けて考えられるのです。
たとえば、職場で注意されたとき。
心が乱れていると「自分はもうダメだ」と感じがちですが、
整っていれば「ミスを直せば次は大丈夫」と冷静に受け止められます。
こうした違いは、仕事のパフォーマンスや人間関係に直結します。
心理的な安定が「判断力」や「思考の整理力」を支えているのです。
② 行動が安定し、習慣が続きやすくなる
気持ちが落ち着いていると、行動にムラが出にくくなります。
「やる気が出たらやる」ではなく、一定のペースで動けるようになる。
たとえば、運動・勉強・家事・仕事──どんなことでも、
感情に左右されずに続けられることが成功の秘訣です。
心を整えることは、「やる気」よりも安定的な力をもたらします。
認知行動療法でいう「行動活性化(Behavioral Activation)」は、
“行動から気持ちを整える”考え方です。
③ 対人関係の摩擦が減る
心が整っていると、相手の言葉や態度に過剰に反応しなくなります。
「どうしてあんな言い方をされたんやろう」と考え込みすぎる時間が減り、
人間関係に余裕が生まれます。
また、他人の気分に振り回されず、自分の境界を保つことができます。
結果として、職場や家庭でのトラブルが減り、
人とのつながりが穏やかで安定したものになります。
④ 集中力・創造性が高まる
慢性的なストレスは脳の扁桃体を刺激し、
注意力や判断力を担う前頭前野の働きを抑えてしまいます。
逆に、心が整うと神経系のバランスが整い、
集中力・記憶力・発想力が自然と高まります。
マインドフルネスや瞑想の研究でも、
「脳の灰白質が増える」「前頭前野の活動が高まる」などの効果が報告されています。
つまり、心を整えることは脳のパフォーマンスを上げることでもあるのです。
⑤ 身体への好影響がある
心と身体は密接に関係しています。
心が安定すると自律神経のバランスが整い、
結果的に次のような身体的メリットが得られます。
- 睡眠の質が良くなる
- 血圧や心拍が安定する
- 胃腸の調子が整う
- 疲れが取れやすくなる
つまり、「風邪をひきにくくなる」身体の整いと、
「ストレスに動じにくくなる」心の整いは、とても似た仕組みなのです。
3. どうすれば「心を整える」ことができるのか
では、どうすれば日常の中で心を整えられるのでしょうか。
特別な訓練や時間は必要ありません。
認知行動療法の基本を生活の中に取り入れるだけでも十分です。
🌱 ① 自分の「自動思考」に気づく
まずは、頭に浮かぶ“自動的な考え”に気づくこと。
「どうせうまくいかない」「また怒られるかも」といった思考をそのままにせず、
「本当にそうだろうか?」と立ち止まってみましょう。
自分の考えに気づくことが、心を整える第一歩です。
🏃♀️ ② 行動を少し変えてみる
気分が落ち込んでいるときほど、動かないと余計に沈みがちです。
「気分が良くなったら動く」ではなく、「少し動くことで整える」。
たとえば、外を歩く・整理整頓をする・好きな飲み物をゆっくり味わう──。
小さな行動の積み重ねが、心の調律になります。
🌼 ③ “いま・ここ”に注意を戻す
マインドフルネスの基本は、「過去や未来ではなく、今に戻る」こと。
頭の中が考え事でいっぱいのときこそ、
呼吸のリズムや足の感覚に意識を向けてみてください。
これはスピリチュアルではなく、科学的に裏づけられた「神経の整え方」です。
4. 「漢方」との共通点 ― “治す”より“整える”
心理支援と漢方には共通点があります。
どちらも「即効性」ではなく、「バランス」を重視している点です。
漢方は身体の“体質”を整え、自然治癒力を引き出します。
心理支援は、心の“反応パターン”を整え、自己調整力を育てます。
つまり、どちらも「症状を消す」のではなく、「回復できる力を育てる」。
この考え方こそが、現代の“セルフケア文化”の基盤になっています。
5. まとめ ― 心を整えるとは「再現性のある平常心」をつくること
身体を整えると、動けるようになる。
心を整えると、動じなくなる。
心を整えるとは、感情の波をなくすことではありません。
波が来ても沈まない“しなやかさ”を育てることです。
カウンセリングとは、その“動じない自分”を取り戻すための時間です。
一度整える方法を身につければ、それは一生使える「こころのメンテナンスツール」になります。
大阪で「心を整えるカウンセリング」をお探しの方へ
認知行動療法カウンセリングセンター大阪店では、
不安・ストレス・人間関係の悩みなどに対して、
「心を整える」ための具体的な方法を一緒に見つけていきます。
📍住所:〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-21 早川ビル303号室
🚋アクセス:近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩2分/谷町九丁目駅 徒歩5分
🕓営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
💬LINE予約:https://lin.ee/26sKHRK8
📝申込フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
⭐Google口コミ:https://g.page/r/CVHhJlc6ZfG5EBM/review