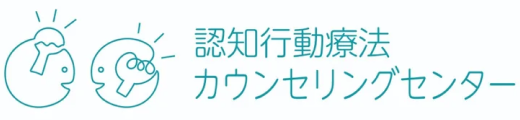2025年07月26日
- ご案内
大阪の認知行動療法研修『成人期発達障害に活かす認知行動療法の技術と視点』

── 金澤潤一郎先生によるオンラインセミナー振り返り(2025年7月開催)
2025年7月、当センター主催のオンライン研修にて、成人期の発達障害支援に特化した認知行動療法(CBT)の研修会が開催されました。講師を務めたのは、臨床現場と研究の双方で長年にわたり活躍されている北海道医療大学の金澤潤一郎先生です。
本記事では、支援職・心理職を対象としたこの研修の学びを、主催者視点で丁寧に振り返ります。
技法より“在り方”を問う学びの時間
研修全体を通じて、金澤先生が何より強調していたのは、支援者の“技術”ではなく“姿勢”でした。
「正しく関わること」や「適切にアプローチすること」よりも、「目の前の人とどのような距離感で、どのような態度で関わるか」が支援の成否を分ける――そんな姿勢が一貫して伝えられていました。
特に成人期の発達障害支援では、「困っている本人」を中心に置いた関係構築が欠かせません。セミナーの中では、支援者側の焦りや介入欲が、いかに支援の妨げになってしまうかについても、事例を交えながら深く掘り下げられました。
自覚なき“正しさの押しつけ”──間違い指摘反射とは?
研修の中盤で紹介された「間違い指摘反射」という概念は、多くの参加者の関心を集めました。
これは、支援者が本人の発言や行動の“ズレ”に気づいた際、つい無意識に「それは違う」と正したくなる反応を指します。
もちろん意図としては「本人のため」なのですが、当事者にとっては「また否定された」「自分の考えは間違っていた」という受け取りになりやすく、結果として“考える力”や“やってみようとする意欲”を削ぐことになりかねません。
金澤先生は、
「指摘して変えさせる」ことよりも、「考えられる余白を残すこと」の方が重要になる局面がある。
と語り、支援者の“反射的な関わり”を意識的に見直す必要性を強調されていました。
傷ついた当事者が抱える“学習された無力感”
否定される経験が蓄積すると、人は「どうせ否定されるなら、もう話さない」「自分で考えるのはやめよう」と学習します。これがいわゆる“学習された無力感”です。
特に発達特性をもつ方々は、幼少期から家庭・学校・職場などで繰り返し否定的な経験をしていることも多く、その積み重ねが“自分を表現することへの恐れ”として定着していることもあります。
支援者が善意で行う指摘が、実はこの“恐れ”を強化してしまっているとしたら――
私たちは何に注意し、どんな態度で関わるべきなのか。支援の原点が、改めて問われる時間となりました。
支援者の立ち位置を捉え直す——「キャディとしての関わり」
金澤先生が用いた比喩のひとつに、「ゴルファーとキャディ」の関係性があります。
実際にコースでプレイするのは当事者(ゴルファー)であり、支援者(キャディ)は、選択肢を示したり、風の流れを伝えたりすることはできても、“打つ”ことはできません。
つまり、「最終的な決定と行動は当事者のものである」という立場を、支援者が常に意識し続けることが重要だというメッセージです。
「何とかしてあげたい」「良くなってほしい」という願いがあるほど、支援者は無意識に“クラブを握ってしまう”危険があります。その“欲”に気づきながら、本人の力を信じ、支える視点を持ち続けることが求められます。
コンパッションとは、矛盾を引き受ける力
コンパッション(思いやり)という言葉は、今や多くの現場でキーワードとして用いられていますが、金澤先生の語る「実践的コンパッション」は、一段深いものでした。
- 「分かってあげたいのに、イライラしてしまう」
- 「同じ話をされることに、うんざりしてしまう」
- 「頑張ってほしいのに、動いてくれないことがもどかしい」
——こうした“矛盾する思い”を持つこと自体は、ごく自然なことです。
重要なのは、その感情を“持ってはいけない”と否定するのではなく、「自分の中にこうした思いがある」と認めた上で、それでも支援を選び続けること。
つまり、コンパッションとは「完璧な共感力」ではなく、「未熟な自分を抱えながらも支援を続ける姿勢」なのだと、金澤先生は語りました。
支援とは、“選択”の積み重ねである
本研修を通して繰り返し伝えられていたのは、支援とはマニュアル通りに進むものではなく、毎瞬「どう関わるか」を選び続ける営みである、ということです。
- 怒らず伝えるか、黙って見守るか
- 問題に切り込むか、タイミングを待つか
- 成果を求めるか、試みを認めるか
…どの選択にも“正解”はありません。
しかし、その選択のひとつひとつが、当事者との関係性に影響を及ぼします。
だからこそ支援者には、「選び続ける覚悟」と「振り返り続ける誠実さ」が求められる――この言葉が、受講後も参加者の胸に強く残ったのではないでしょうか。
研修主催者からのあとがき
今回の研修は、支援の「技法」を学ぶというよりも、「姿勢」「構え」「覚悟」といった、“支援者としての土台”を見直す機会となりました。
チャット欄でのやり取りや終了後の感想では、「今日からの関わりが変わりそう」「自分の支援の癖に気づかされた」といった声も多く見られ、私たち主催者としても手応えを感じています。
今後もこのような“立ち止まって振り返る場”を継続的に提供していければと願っております。
🎥録画視聴について
本セミナーは録画視聴も可能です。ご都合が合わなかった方や復習したい方は、下記のURLからお申込みいただけます。
お申込みはこちら:
https://peatix.com/event/4449707/view
🏢 認知行動療法カウンセリングセンター大阪店
- 住所:〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-21 早川ビル303号室
- アクセス:近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩2分、谷町九丁目駅 徒歩5分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://osaka.cbt-mental.co.jp/
👨🏫 登壇講師プロフィール
金澤 潤一郎(かなざわ じゅんいちろう)先生
北海道医療大学 心理科学部 准教授。臨床心理士・公認心理師。
成人期ADHDや発達障害に対する認知行動療法の実践と研究に従事し、精神科医療・心理支援・教育支援の幅広い領域で活躍中。
アジアADHD学会でPoster Abstract Awardを受賞。近年は支援職向けの倫理的実践・支援姿勢に関する講演にも定評がある。