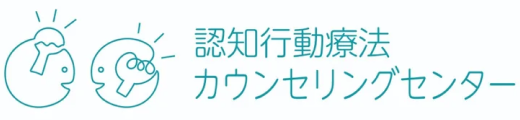2025年07月15日
- 認知行動療法
大阪で社交不安で人付き合いがつらい方へのカウンセリング

~不安と「楽しめなさ」の両方に向き合うCBT支援~
こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター大阪店です。
「人と話すときに変に思われていないか不安になる」
「会話が終わった後、自己嫌悪に陥ってしまう」
このような社交不安症に関するご相談は、年齢・性別を問わず多く寄せられています。
ただ最近では、不安だけでなく、次のような声が目立ってきています。
「そもそも人といても楽しくない」
「話せるようになっても、嬉しさや満足感が得られない」
この状態は、**アンヘドニア(快感喪失)**と呼ばれるもので、社交不安症と同時に現れることもあります。
本記事では、社交不安とアンヘドニアの関係性と、CBT(認知行動療法)での支援方法をご紹介します。
アンヘドニアとは何か
アンヘドニアとは、喜びや楽しみの感覚が鈍くなり、感じづらくなる状態です。
うつ病でよく知られている症状のひとつですが、社交不安症の方にも見られることがあります。
特にこんな状態が見られます:
- 人と一緒にいても、気持ちが温まらない
- 雑談しても空虚さや疲労感だけが残る
- 褒められても心に届かない
- 会話中に笑顔が出ない・返ってきても無感覚
このような状態では、「人と関わりたい」という動機づけ自体が弱まりやすくなります。
社交不安とアンヘドニアが絡む仕組み
恐怖に加えて「報われなさ」も
社交不安症では、人との関わりにおける「評価されるかも」「恥をかくかも」といった不安が中心になります。
しかし、**「関わっても面白くない」「得るものがない」**という感覚が根底にあることも少なくありません。
報酬系の感受性が下がっていることも
近年の脳科学の研究では、社交不安症の方が人間関係におけるポジティブな刺激(微笑み、共感、受容など)を受けた際、
脳の報酬系(快感を司る領域)の活動が低いことが示されています。
このため、「社交=疲れるだけ」「どうせ嬉しくない」といった回避的な考えが強まってしまうのです。
行動しないことで、ますます孤立しやすくなる
「どうせ意味がないから行かない」→「人間関係が減る」→「孤独が強まり喜びも減る」
このようなサイクルは、社交不安+アンヘドニアの特徴的な悪循環です。
CBT(認知行動療法)による支援のアプローチ
CBTでは、不安の軽減だけでなく、「感情が動く体験」を意識的に増やしていくことが支援の柱になります。
◆ 行動活性化:心が動かなくても、まず体を動かす
行動活性化とは、**今は楽しくなくても“とりあえずやってみる”**という経験から、心の動きを育てていくアプローチです。
- 「楽しかったかどうか」より「やってみたかどうか」に注目
- どんな些細なことでも“関われた”事実を記録
- 「しんどくなかった」「思ったより悪くなかった」といった中間的な感覚も評価対象にする
例:
● 出勤時に目が合った人に軽く会釈してみる
● 無理に雑談しようとせず、1対1で2分間だけ話す
● コンビニの店員と「ありがとう」だけ交わしてみる
◆ 喜びを再発見するための工夫
「喜びを感じましょう」と言われても、アンヘドニアの状態では難しいものです。
CBTでは、“感じた微細な変化”を丁寧にキャッチする練習を行います。
- 1日を振り返り、「少しだけマシだったこと」を書き出す
- 「相手が笑ってくれた」「黙っていても気まずくなかった」などの観察
- 喜びではなく「不快でなかったこと」も肯定的に扱う
仮想ケース紹介:20代・男性Aさん
Aさんは、会議や対面の雑談で強い緊張を感じ、社交の場面を避けるようになっていました。
さらに、「人といても何も感じない」「一人の方がラク」といった感覚を口にするようになり、自発的な行動がほとんどなくなっていました。
最初は暴露法(苦手な場面に段階的に挑戦)を試みましたが、
「何も変わらない」「意味がない」と感じることで継続が困難に。
そこで、
- 人と話した後の「不快ではなかった時間」をメモ
- 自分が“少しだけ安心できた”感覚に注目
- 関わる価値を「楽しいかどうか」ではなく「嫌ではなかったか」で評価する
という形に切り替えたことで、徐々に関わる感覚が戻ってきました。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 楽しめなさが強い場合、治療は長引きますか?
→人によりますが、行動量が増えてくると「気づき」が生まれやすくなり、少しずつ心が動き始める方も多いです。
Q2. CBTって実際にどうやってやるんですか?
→日常の行動記録や、会話中の自分の感情・思考を整理するワークを行いながら、少しずつ変化を積み重ねていきます。
Q3. 人と話すのが本当に怖いです。顔出しなしでも受けられますか?
→はい。オンラインでも顔出しなし・音声のみの対応が可能です。無理のない範囲から始められますのでご安心ください。
まとめ
| ポイント | 内容 |
| 社交不安の特徴 | 緊張・恐怖だけでなく「喜びがない」も影響大 |
| CBTでの支援 | 行動活性化+報酬感受性の再構築 |
| 進め方 | 無理せず、小さな変化に気づく練習から |
| ゴール | 喜びを感じる“きっかけ”を増やしていくこと |
大阪で社交不安と「楽しめなさ」にお悩みの方へ
「人と関わるのがしんどい」
「怖いというより、無意味に感じてしまう」
そんな思いを抱えている方も、どうぞ一度ご相談ください。
認知行動療法カウンセリングセンター大阪店では、
社交不安とアンヘドニアの両方に対応した専門的な支援を行っております。
■ 認知行動療法カウンセリングセンター大阪店
- 所在地:〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-21 早川ビル303号室
- アクセス:近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩2分、谷町九丁目駅 徒歩5分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- ご予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://osaka.cbt-mental.co.jp/