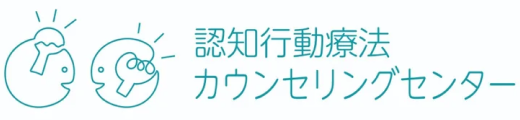2025年09月29日
- 認知行動療法
大阪で嘔吐恐怖へのカウンセリング

嘔吐恐怖(エメトフォビア) とは、「吐いてしまうのではないか」という強い不安や恐怖が続き、生活全体に支障が出てしまう状態を指します。外食や学校、仕事の場面だけでなく、電車やバスの移動でも強い不安を感じることがあり、社会生活に大きな影響を与えることも少なくありません。本人にとって深刻な問題であるだけでなく、家族にとっても負担となることがあります。
こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター大阪店です。
当センターは大阪市天王寺区に拠点を構え、地域の方々が安心して相談できる場として、認知行動療法(CBT)に専門特化したカウンセリングを提供しています。
今回のテーマは 「嘔吐恐怖(エメトフォビア)」。この記事では、その特徴や背景、そして認知行動療法によるカウンセリングの流れについてご紹介します。
嘔吐恐怖とは?
嘔吐恐怖は、単に「吐きたくない」「気持ち悪いのが嫌だ」という感覚を超えて、
- 自分が吐いてしまうこと
- 他人の嘔吐を目撃すること
- 人前で吐くこと
を強く恐れる状態です。
この恐怖は「また吐いたらどうしよう」という 予期不安 と結びつきやすく、外食や会食を避ける、公共交通機関を使うのが難しくなる、職場や学校で人との交流から距離を置いてしまう――といった行動につながります。その結果、学業や仕事、人間関係に深刻な支障が出てしまうこともあります。
嘔吐恐怖に見られる悪循環
典型的には、次のようなサイクルが見られます。
- きっかけ
「少し気持ち悪いかも」「吐いたらどうしよう」という思い。 - 身体反応
動悸、発汗、喉のつかえ、胃のむかつきといった身体症状。 - 注意の集中
体の感覚に過剰に意識が向き、不安がさらに高まる。 - 回避行動
外食を避ける、席を立つ、体調を繰り返し確認するなどの行動。 - 不安の固定化
一時的な安心は得られるが、「避けなければ危険だ」という思い込みが強化され、不安が悪化していく。
このように、回避行動が一時的には安心をもたらすものの、結果的に恐怖を強めてしまいます。
認知行動療法(CBT)の取り組み
嘔吐恐怖へのカウンセリングでは、認知行動療法(CBT) が有効とされています。CBTでは「考え方」と「行動」の両面に働きかけ、悪循環を変えていきます。
1. 症状の理解と整理
不安や恐怖がどのように始まり、どの場面で強まるのかを整理します。悪循環の流れを一緒に確認し、「なぜ不安が続いているのか」を理解することから始めます。
2. 暴露療法(エクスポージャー)
不安を避けず、少しずつ行動を試していきます。
- 「外食の場に座る」
- 「少量を口にしてみる」
- 「不安があっても席に残って過ごす」
こうした段階的な練習を重ねることで、「不安や恐怖があっても行動できる」という体験を積み上げていきます。
3. 行動実験
「吐いたら必ず大変なことになる」「人に迷惑をかけてしまう」という思い込みを実際に検証します。
たとえば、友人と軽くお茶をする、外食で少量だけ食べる、不安があっても席を立たずに続けてみるなど。観察を通じて「思っていたほど深刻な結果にはならなかった」と気づく体験を積んでいきます。
4. 注意のシフト
身体の感覚ばかりに意識が集中するのを防ぐため、注意を他に向ける練習をします。
- 食事なら味や香りに意識を向ける
- 会話なら相手の表情や話の内容に集中する
- 移動中は周囲の景色や音を観察する
不安を消すためではなく、不安があっても他のことに意識を向けて行動できる 感覚を体験することが狙いです。
5. 認知のとらえ直し
「吐いたら終わりだ」「人前で吐いたら取り返しがつかない」というような厳しい受け止め方を、そのままにせず、別の視点から考える練習をします。
- 実際に吐いた回数はどれほどあったか
- 吐いても周囲は思ったほど気にしていないのではないか
- 不安が強くても、何とかその場にいられた経験がある
こうした気づきを重ねることで、「不安や恐怖があっても大丈夫なときがある」と柔軟に考えられるようになり、行動の幅が広がります。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 嘔吐恐怖は薬で改善できますか?
A. 薬で一時的に不安を和らげることはできますが、根本的な改善には心理的な取り組みが必要です。当センターでは認知行動療法を中心に行っています。
Q2. 嘔吐が不安で職場や学校に行けません。相談できますか?
A. はい。外食や通勤・通学、人前での活動に不安を抱える方のご相談にも対応しています。段階的に取り組めるようサポートいたします。
Q3. 遠方に住んでいても利用できますか?
A. はい。当センターでは全国対応のオンラインカウンセリングを実施しており、大阪市外や関西圏以外からもご利用いただけます。
ご利用案内
認知行動療法カウンセリングセンター大阪店
- 住所:〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-21 早川ビル303号室
- アクセス:近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩2分、谷町九丁目駅 徒歩5分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://osaka.cbt-mental.co.jp/
まとめ
嘔吐恐怖は「吐くかもしれない」という恐怖心が生活を狭めてしまうつらい症状ですが、認知行動療法によって改善が期待できます。
「安心して外食したい」「人との関わりを自然に持ちたい」――そんな願いをサポートするのが大阪店のカウンセリングです。
嘔吐恐怖に振り回されず、自分らしい生活を取り戻す一歩を、ぜひ一緒に踏み出してみませんか。
一覧に戻る