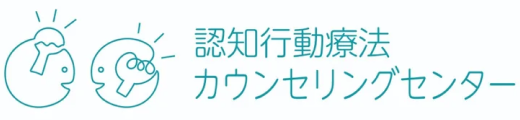2025年09月28日
- ご案内
大阪の認知行動療法研修『睡眠障害へのカウンセリング』

──岡島義先生 オンラインセミナーレポート(2025年9月開催)
「眠れない」「寝ても疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚める」——それ、睡眠障害かもしれません。
睡眠の質は、私たちのメンタルヘルスや日常生活に大きな影響を与えます。
うつ、不安、発達特性といった困りごとを抱えている方の多くが、「実は眠れていない」という背景を持っています。にもかかわらず、現場ではその支援が感覚的・経験的に行われがちです。
こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター大阪店です。
2025年9月27日にZoomで開催されたオンライン研修『事例で学ぶ睡眠障害への認知行動療法』には、全国各地の心理職・支援職の方々が多数ご参加くださいました。
講師は、睡眠支援における臨床と研究の両輪で活躍されている岡島義先生(東京家政大学 教授)。
本記事では、研修を通して得られた気づきや印象的な場面について、主催者の視点からご紹介します。
睡眠は“ついで”ではなく、支援の本丸になりうる
前半では、睡眠のメカニズム(恒常性・概日リズム・覚醒系)や、不眠の成り立ちについての理論を明快に整理したうえで、CBT-I(不眠症に対する認知行動療法)の構成要素が詳しく解説されました。
岡島先生は、睡眠支援を「他の問題が解決すればついてくる副産物」としてではなく、独立した支援対象として捉えるべきだと繰り返しお話されていました。
これは大阪店でも、実際のカウンセリング現場で感じていた課題と重なります。
「眠れないから仕事がうまくいかない」「昼間眠くて集中できず自信をなくす」といった訴えは、軽視すべきものではないのです。
参加者からも、「これまで曖昧にしていた部分が言語化された」「睡眠の話をもっと聞きたくなった」との感想が寄せられました。
自分の生活を振り返る時間にもなった
個人的に印象深かったのは、支援者としての学びだけでなく、自分の睡眠習慣を見直すきっかけにもなったことです。
岡島先生が語った、「眠れないのは意志の弱さや生活のだらしなさではない」という言葉が、どこか心に残りました。
夜更かし、寝付きの悪さ、休日の寝すぎ。
“ちょっとした不調”の積み重ねが、日中の思考や気分、そして支援の質にも影響を与えるのではないか——そんな視点に立てたことで、日々の過ごし方を見直そうと思えました。
事例紹介:理論と実践をつなぐ
後半では、岡島先生が実際に行ったCBT-Iの事例が紹介されました。
睡眠日誌から始まり、見立て、睡眠スケジュール法の適用、評価のポイント、そして終結までの全体の流れが丁寧に語られました。
印象に残ったのは、「変化の兆し」にどう注目し、どう言語化するかという部分。
たとえば、「記録が取れなかった」ことに焦点を当てるのではなく、“意識が向いたこと”を価値として扱う姿勢が貫かれていました。
支援者が陥りやすい“できた・できなかった”という二項対立ではなく、
「どこに意識が向いていたか」「どんな努力があったか」に光を当てるアプローチに、深い臨床センスを感じました。
“ユーモア”という技術的な関わり
岡島先生の講義で印象的だったのが、“ユーモア”の扱い方です。
それは決して場を和ませるための冗談ではありません。
クライエントが自責に陥った瞬間に、「そのままで大丈夫ですよ」と伝える介入技術としてのユーモアです。
たとえば、「記録が取れていなくてすみません」と謝るクライエントに対して、
「“取らなきゃ”と思っていた時間、それが最高のCBTですよ」と返すやりとり。
それは軽さや笑いを届けるだけでなく、「評価ではなく価値に目を向ける」姿勢をユーモアという“かたち”にして届けているのだと感じました。
睡眠支援の本当のゴールとは
CBT-Iというと、「何時間眠れるようになったか」「夜中に目覚めなくなったか」といった“結果”に目が行きがちです。
しかし岡島先生は、次のように語ります。
「CBT-Iの目的は“よく眠ること”ではなく、“その人らしい日中の生活を取り戻すこと”です」
眠ることが目的なのではなく、
「眠れなかったことで諦めていた仕事、趣味、人付き合いなどを、再びできるようにする」——
この視点を持って睡眠を支援することの大切さを、改めて実感しました。
Q&A:現場に根ざした質問に丁寧に回答
最後に行われた質疑応答の中から、特に印象的だったやりとりを2つご紹介します。
Q:昼夜逆転が続いている方に対して、支援はどこまで踏み込んでいいのでしょうか?
A:
ご本人が「このままじゃ困る」と感じている場合には、CBT-Iの適用は有効です。
ただし「生活リズムを整えてあげたい」という支援者の気持ちが強くなりすぎると、逆に関係性を損なうこともあります。
まずは“その人の困りごと”をきちんと共有することがスタート地点です。
Q:睡眠薬を使っている方に対してもCBT-Iは可能ですか?
A:
もちろん可能です。むしろ、薬の効果に不安を感じている方には、「自分で調整できる感覚」を育てる支援が非常に効果的です。
CBT-Iは“減薬”のためにあるのではなく、“コントロール感”を取り戻すために行うのだと捉えると良いでしょう。
登壇講師プロフィール
岡島 義(おかじま いさ)先生
東京家政大学 教授(睡眠行動科学研究室)
公認心理師・臨床心理士/認知行動療法師
日本睡眠学会専門心理師・専門行動療法士
睡眠障害への認知行動療法(CBT)の臨床と研究に長年従事し、多くの賞を受賞。
現在も複数の学会で理事・評議員として活躍されており、臨床・教育・普及のすべてに携わっておられます。
アーカイブ配信、現在受付中!
当日の講義は録画配信を行っています。
当日ご都合が合わなかった方や、もう一度じっくり復習したい方は、ぜひ以下よりお申し込みください。
📅 アーカイブ申込ページ(Peatix)
👉 https://peatix.com/event/4517633/view
※配信は期間限定です。お早めにお申し込みを。
認知行動療法カウンセリングセンター大阪店のご案内
- 住所:〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-7-21 早川ビル303号室
- アクセス:近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩2分、谷町九丁目駅 徒歩5分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://osaka.cbt-mental.co.jp/